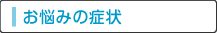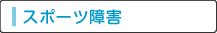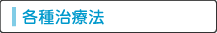- ビタミンDについて
-
1980年代よりビタミンDの効能は様々な分野で報告されています。
「骨粗鬆症」、「ほとんどすべてのがん」、「感染症」、「炎症性腸疾患」、「糖尿病」「多発性硬化症」「自己免疫疾患」「アトピー」「関節リウマチ」「花粉症」「慢性疼痛」などなどです。
下記に記しているのは2012年6月29日私がブログで書いた内容です。この中で述べているように、難治性の様々な疾患にビタミンD不足が関与している可能性があります。
もし不足していたら、ビタミンDの内服を含めて何らかの対応が必要です。当院では血中ビタミンDを測定して低下していれば1000-10000IUの不活化型のビタミンDの内服をお勧めしています。
血中濃度を測定しなくても例えば「アトピー」「関節リウマチ」「花粉症」「関節リウマチ」の方は1日1000-2000IUの不活化型のビタミンDを試すべきではないでしょうか。
一般的に言われている過剰症は1日40000IU(4万IU)以上を長期服用で報告されているため、ほとんど過剰症は心配しなくてもいいでしょう。
また様々な測定結果から白人より黒人や黄色人種は日光暴露にかかわらずビタミンD血中濃度は低いことがわかってきています。
この現実を踏まえて考えてみると、私たちのほとんどの方が、がんや様々な疾患の予防目的で1000-2000IUの不活化型のビタミンDを内服すべきではないでしょうか。不活化型ビタミンDというのは、体内で腎臓を含め様々な臓器や免疫細胞で活性酵素から活性型ビタミンDに変換されます。
保険適応の活性型ビタミンDは、それとは違い骨に選択性をもたらしている点が大きく異なり、量的にも数百分の1程度です。
つまり、量的にも足りないことと骨粗鬆症含め、不活化ビタミンDの方が圧倒的に効果的である、ということです。
血中の不足が予想され紫外線暴露ができない方は、不活化型ビタミンDを食物、サプリなどにて補充する必要があるということになります。
当院ブログ(2012.6.29)
骨だけではなかった!驚くべき可能性ビタミンD その1(がん、感染、腸疾患、多発性硬化症など……)
- 驚くべき可能性ビタミンD (がん、感染、腸疾患、多発性硬化症など……)
-
ビタミンDと言えば、古臭い骨粗鬆症の薬剤くらいにしか評価されていない。
しかし「多種類のがん」、「感染症」、「炎症性腸疾患」、「1型糖尿病」「多発性硬化症」などに効果があると言われている。
なぜだかわからないが、20世紀初頭の抗生物質誕生以前に「結核」に「日光浴」が効果的であることがわかっていた。
「結核」だけでなく日光を浴びれば骨の疾患である「くる病」なども治ることがわかっていた。 - ビタミンDの合成経路
-
ビタミンDは他のビタミンと違い体内で合成が可能である。
皮膚に紫外線を当てると「コレステロール」を原材料にしながら活性型のビタミンDを作る。
しかし多くの皮膚で合成された不活性型のビタミンDは、食物由来の不活性型のビタミンDとともに血液循環に入り、肝臓・腎臓で活性型に変化していくが、必要とあれば免疫細胞等でも腎臓と同じ酵素を利用して、活性型ビタミンDを作っている。
ここで注目すべきは、コレステロールと紫外線があれば皮膚で活性型ビタミンDを合成できる事実だ。 - がんを抑制するビタミンD!!
-
1980年代以降ビタミンDの投与が「がん」の発生を抑えることがわかってきた。
マウスにビタミンDを投与すると頭頸部の「がん」が80%抑えられることがわかっており、前立腺がん、乳がんの動物モデルでも同様のことが得られている。
ビタミンDの血中濃度が低いと大腸がん、前立腺がん、乳がんの発症が30-50%高くなり、ノルウェーやフィンランドなどの高緯度に住む女性は赤道付近に住む女性に比し卵巣がんの発生が50%高かった。
1100IUのビタミンDを3年間毎日摂取したネブラスカ州在住の55歳の以上の女性集団はすべのがんの発生率が77%低かった。
大腸がん、乳がん、膀胱がん、卵巣がんの発症率はアメリカでは南から北へ行くと2倍に上がる。 - なぜビタミンDに効果があるのか
-
ビタミンDはほぼすべての組織での遺伝子のスイッチのON OFFに関与している。
ビタミンDは遺伝子が収められている核内に入り込み、ある特定のたんぱくと結びつき、さらに別のたんぱくと結びついてDNAの特定の部位に結びつき遺伝子を発令させ、生体内でたんぱくを作らせる。
この細胞核に直接作用して特定のたんぱく質を生体内作らせることがビタミンDの生理活性となる。
この様に核内の受容体に結びつくものをスーパーファミリーと呼びそれらは生命維持の根源的役割をもつ。
ビタミンDが影響する遺伝子は1000種類を超える。
代表的なものは骨代謝に関与するものだが、「がんの予防」、「感染症」、「炎症を抑える」など様々である。
「感染症」に関するものだが、体内で抗菌ペプタイドを作る遺伝子の近くにビタミンDの受容体たんぱくがあり、人の細胞にビタミンDを加えるとこの抗菌ペプタイドを作るのも確認されている。
またビタミンDが炎症際の過剰なサイトカイン(情報伝達物質)を抑え過剰な炎症を抑えることが確認されている。 - ビタミンDと日光照射、食物
-
食物や日光照射からどれほどとれるかを少し記載しておく。タラ肝油1360IU/大さじ1杯、マグロ、イワシ、サバ、サケなどは200-360IU/85-100g、生シイタケ100IU/100g、干しシイタケ1600IU/100g、卵黄20IU/1個である。
そして夏の昼間白人が15-20分間直射日光に暴露されたときは10000IU体内で合成できる。
ここで白人であるとことわっているのは、皮膚が白いほうが紫外線の吸収が良いためだ。
色が黒いと吸収率は1/6に低下し黒人の場合ビタミンDの血中濃度は白人の半分にとどまっている。 - 多発性硬化症はビタミンD不足の可能性
-
ビタミンDは自己免疫疾患にたしても有効の可能性がある。
多発性硬化症は脳や脊髄の神経のミエリン鞘に免疫細胞が攻撃を仕掛けて多彩な神経症状を引きおこす。
この疾患は以前から赤道から離れる地域に発生頻度が高くなることが知られている。
また季節変動もあり、春に増悪して秋には軽くなるのだ。これは冬の間日照時間が少なく、夏に多いためビタミンD濃度が春に最低になり、秋に最大になることと一致する。
南カルフォルニア大学が79組の一卵性双生児の中で幼いころ屋外でよく遊ぶ子供は外で遊ばない兄弟、姉妹より発症率リスクが57%低かった。
ハーバード大学の公衆衛生大学院のチームは700万人の海軍、陸軍の結成保存サンプルから多発性硬化症を発症したサンプルのビタミンD濃度は低かった。つまり血中濃度が40ng/mlを超える兵士の発症リスクは25ng/ml以下の兵士より62%も低かった。 - ビタミンDが影響している臓器
- ビタミンDが遺伝子に働き影響していることが証明されている臓器は骨、肝臓、脳、神経細胞、乳房、膵臓、脂肪、副甲状腺、腸、免疫細胞、前立腺、腎臓、皮膚などの全身ほとんどすべてであるし、この先他の部位も働きがわかる可能性がある。
- ビタミンD欠乏を防ぐには
-
皮膚からの紫外線吸収が最も安価で効率的だが日焼け止めクリームを塗ると98%がブロックされる。
日光照射で少し赤みが出る程度に当たらなければいけない。必要量の紫外線は北米で真夏に10-15時の時間帯に5-15分の全身紫外線暴露が必要である。
この照射は多すぎても意味がないばかりでなく、ビタミンDを壊す物質さえ作ってしまうし、紫外線の他の害もでてくることになる。
しかし日光暴露の少ない地域では経口から摂取するビタミンDを増やすしかない。
どのくらい摂取すべきかは日本での基準は200IU(5μg)で欧米では200-600IU(5-15μg)とかなり差があり、ハーバード大学では1000IU(25μg)を推奨している。
またこの参考文献の著者は毎日4000IU(100μg)を摂取しているなど量に差がありすぎるし、日光照射の影響をどのくらいに見積もるかは難しい。
血中濃度との様々な疾患との相関から25-45ng/mlというのが適切な値の様だ。
この値からさらに上昇して150ng/mlを超えると高カルシウム血症などの中毒症状がでてくる。
まずは皮膚を日光に暴露することを極端に恐れないことが必要である。
それに自分の地域や生活パターンが日光に暴露される機会が少なければ、やはり500-1000IU程度のビタミンDは摂取すべきかもしれない。
感染症、自己免疫疾患、がんなどにすでにかかっていたり、その可能性が高い場合は、ビタミンDの血中濃度を測定して日光照射を増やすことがまず行うべきことと、日光照射の少ない秋から冬にかけて積極的にビタミンDの摂取を増やすなどの、適切な対応を考えるべきであろう。 - 花粉症
-
斉藤糧三先生は日本機能性医学研究所を立ち上げ、ビタミンDの効能をいち早く日本に紹介している。
彼の著書「サーファーに花粉症はいない」を読んでみたが、予想通り様々な疾患によく効くことを紹介している。
その中でも面白かったのは「花粉症」「アトピー」「リウマチ」に対してのものである。 - 花粉症の従来の治療
-
免疫とは異物とみなしたものに対して排除する行為をいう。
花粉症の際の異物とはスギやヒノキなどの花粉が眼球や鼻粘膜に侵入した際に異物とみなし排除される際の反応をいう。
この反応に免疫細胞として白血球が関与している。さらにこの免疫が適切に行われいればいいのだが、過剰になり大変なことが起こるのである。
治療法としては花粉に触れないようにするために、マスク、メガネの着用から始まり症状を抑えるのに抗ヒスタミン剤(眠たくなる薬)、抗アレルギー剤(すぐには効かず2-3週間前より内服)そしてステロイド(副腎皮質ホルモン剤)の内服となる。
これらの薬物治療の効果が期待できない場合は、鼻粘膜の焼却などをおこなう。これとて根治というわけではなく再発も多い。
減感作療法は花粉症の原因となるスギやヒノキの成分を少しずつ口腔内や皮膚から体内に入れることで、身体に免疫を起こさせない免疫寛容を作り出すことで花粉症を治している。
最近は栄養療法として炎症を抑えるオメガ3系の油を使用する。
これは主に魚油を中心としたEPA,DHAなどの油ということになるが、即効性はあまりないが長期の結果はそれなりに効いているようだ。 - 花粉症のビタミンDの効果
-
斉藤糧三先生によればビタミンDの花粉症に対する効果は免疫調整ホルモンと位置付けている。
つまり花粉症に際に出現する過剰な免疫を調整しているということだ。
さてビタミンDが花粉症に効くとしているが、彼は自分で4000IUのビタミンDを内服してその結果を報告している。
「サーファーに花粉症はいない」の原文から
飲んで30分くらいして、なんとなく「日なたぼっこ」した時の、ホンワカした気分になってきたのでした。
そして、1時間もしないうちに鼻の奥の窮屈な感じが和らいできていくではありませんか、鼻をかむと、白く粘性の高い鼻汁が出てきて、なんとその後は「鼻にストローを突っ込んだようなスムーズな鼻通り!」鼻はこれくらい空気を通すのだな、と思うくらいのオドロキの変化でした。
この一節の表現はビタミンDが花粉症に対して即効性があり効果は抜群であるといっているし、その後もビタミンDを飲み続け花粉症を治しているようだ。 - 当院のビタミンDの効果
-
私も多少の花粉症があり4000IUのビタミンDを内服すると彼ほどではないにしろ鼻の通りが良くなったことを実感している。
その後アトピーの方、潰瘍性大腸炎の方、花粉症の方に3000IU のビタミンDを内服してもらったところ面白いことに重症度が高い方は一様に「体が暖かくなってくる」と感じている。それも内服20分ほどで体感しているようだ。
ビタミンDに血管拡張作用があるわけではなく、身体が暖かくなるのは別の作用で血流の増加が生じていると考えていいだろう。
核の内部に入り込み遺伝子のスイッチをONにして血流増加するには時間が短すぎる。なにか別の作用があるのではないか。
そしてこの暖かさはみなさん心地よさを感じているようだ。この先重症度の高い方はビタミンDの内服を進めてみることにする。
サーファーに花粉症はたくさんいる
「サーファーに花粉症はいない」の中に書いてあったが「サーファーに花粉症はたくさんいる」のが現実のようだ。
ビタミンD血中濃度を測定すると以外にも低い方が多くおられ、花粉症になっているようだ。
ウェットスーツの着用や日焼けして紫外線の吸収が悪くなっているのが原因のようだ。
「サーファーに花粉症はたくさんいる」のであれば、日焼けをしているといってもビタミンD濃度は低いこともあることを銘記すべきである。 - 日光浴によるビタミンD合成
-
ビタミンDが日光から皮膚で合成可能なことは別紙にて書いた。
ではどの程度の日光が必要で、時間はどのくらいで、どのくらいのビタミンDが合成可能であろうか。
この問題の答えを得るためにはいくつかの条件がある。
赤道からの距離(緯度)と季節、紫外線が地表に届くときの雲や大気の汚染の状態、肌の色、肌を露出しているか否かの服装、体脂肪の量、日焼け止めを使用しているか否か、年齢などである。
断わっておくが、紫外線の中でビタミンDを合成できるのはB波のみである。 - 緯度と季節、雲・大気の汚染の程度
-
緯度が高くなると紫外線量は減る。
北半球であれば北緯34度以南ならば通年合成可能であり、日本ならばほぼ関西より以南ということになる。
北緯41度(青森の弘前)以北なら11月から2月はビタミンDの合成はできない。北緯34-41度はその中間といったところか。
しかしこれらの条件でも大気汚染や雲の量が多ければ当然、紫外線量は減る。
別のブログで書いたように近年太陽の黒点活動の低下とともに宇宙線の量が増加する可能性あり、そうなれば雲の量は増し紫外線量は減る。 - 肌の色、服装、体脂肪の量、年齢
-
肌の色は白い方が紫外線の吸収は良好であり、日焼けで紫外線吸収は落ちる。
紫外線B波は服を透過できないため、肌を露出する必要がある。
体脂肪はビタミンDを蓄積するため血中濃度を上げるにはより多くの紫外線暴露が必要だ。
加齢は皮膚のビタミンD合成能力を低下させる。
例えば同じ条件での紫外線暴露に対して22-30歳の若者集団と62-80歳の老人集団での最大血中濃度は前者が30ng/mlで後者が8ng/mlであった。 - 日焼け止めクリーム
-
「The Vitamin D Solution」の著者であるマイケル・ホリック博士によればSPF8の日焼け止めでビタミンDの合成は97.5%、SPF15で99.5%減少するといわれる。
彼によれば日本人の場合に半ズボン、半そでで日中の日の高い時間帯に10-15分の日光浴をすれば経口した時の800-1500IUのビタミンD量が合成できるとしている。 - 紫外線の害
-
紫外線は元来皮膚に対して障害を持ち、最も恐ろしいのは皮膚がんである。
この場合日光照射後皮膚が赤くなるだけで日焼けをしないタイプは皮膚がんになりやすいといわれている。
また鉄不足やビタミンCの不足がある方はシミ、そばかすなどの色素沈着が起こりやすい。
このような方たちや紫外線アレルギーがある方は経口で食物やサプリで補うしかないであろう。 - 日焼けをしていても油断するな!
-
前回のブログにも書いたが「サーファーに花粉症はたくさんいる」のであり、日焼けをしているといってもビタミンD濃度は低いこともあることを銘記すべきである。
もしビタミンD不足に心当たりがあれば血中濃度測定が必要だ。 - ビタミンDの血中濃度
-
ビタミンDの血中濃度と様々な疾患との関連がある可能性がある。
表1は斉藤糧三先生の「サーファーに花粉症はいない」から引用したものである。6月下旬に私を含め3人のビタミンD濃度を測定している。 - 血中ビタミンD濃度34.1ng/ml
-
私は今年の10月13日で57歳で特に基礎疾患はない。
私のビタミンDの血中濃度は34.1ng/mlである。表1の中で至適濃度(50-80 ng/ml)に入っていないが、欠乏という範疇からはやっと外れている。
紫外線にあたっているのは朝15分程度の通勤の際の徒歩の時くらいで、休みの日散歩する以外はほとんどない。食事からの摂取は大食漢であるためビタミンD濃度上昇にやや有利に働いているだろう。 - 血中ビタミンD濃度16.8ng/dl
-
70歳代の女性で潰瘍性大腸炎の診断を受け内科でペンタサ、アサコールの内服をしている。
彼女の血中ビタミンD濃度は16.8ng/dlである。「大腸がんの発病リスクが75%増加する」に入っており、「くる病のリスク増加」一歩手前である。
彼女は数か月前に外傷なしで腰椎の圧迫骨折を起こしている。ビタミンD濃度低下による「くる病に近い骨粗鬆症」の状態になっているのだろう。 - 血中ビタミンD濃度18.2ng/dl
-
60歳代の女性で大腸がんの手術後である。彼女の血中ビタミンD濃度は18.2ng/dlである。先ほどの女性と同じく「大腸がんの発病リスクが75%増加する」に入っており、やはり「くる病のリスク増加」一歩手前である。
ほとんどのサラリーマンたちは私と同じように日中紫外線を浴びる機関に恵まれていない。
私の場合食事から摂取する分が比較的多かったため、この値に留まっているかもしれない。
私より紫外線・食事からビタミンDの恩恵を授かれない多くの方がおられるだろう。
上記の2名は私より年齢が上で皮膚の老化の影響もあり、低血中ビタミンD濃度が続いた結果の発病かもしれない。
| ●ビタミンDの血中濃度と関連疾病 | |
|---|---|
| ビタミンD濃度 関連疾病の発現率の変化など | |
| 10ng/ml以下 | 重症欠乏症 |
| 15ng/ml以下 | くる病のリスク増加 |
| 20ng/ml以下 | 大腸がんの発病リスクが75%増加 |
| 30ng/ml以下 | 「欠乏症」骨破壊が進行、骨粗鬆症が進行。創の治癒が遅くなる。筋痛の発症率が増す。関節痛、腰痛の発症率が増す。うつ、統合失調症の発症率が増す。糖尿病の発症率が増す。片頭痛の発症率が増す。自己免疫疾患、アレルギー疾患の発症率が増す。子癇の発症率が増す。 |
| 30~50ng/ml | 「正常値」欠乏が起こらない値 |
| 34ng/ml以下 | 心筋梗塞の発症率が2倍に増加 |
| 36ng/ml以下 | 高血圧の発症率が増加 |
| 40ng/ml以下 | 多発性硬化症の発症率が3倍に増加 |
| 50~80ng/ml | 「至適値」発症リスクを最小限にする値 |
| 50ng/ml以上 | 乳がんの発症率が1/2に減少 固形がんの発症率低下 |
| 80~100ng/ml | がん患者のがんの成長率が遅くなる |
| 100ng/ml以上 | ビタミンD中毒症状の発症率が増す(高カルシウム血症) |
| ビタミンDは25(OH)ビタミンDである。1.25(OH)ビタミンDではない | |
| 検査会社の基準値は40ng/ml以下であるが至適濃度は50ng/ml以上とする | |
| 子癇とは妊産婦の高血圧を原因とする痙攣や失神発作 | |
表1
斉藤糧三著「サーファーに花粉症はいない」から
参考文献
Luz E.Tavera-Mendoza/JohnH.White:ビタミンDの多彩な効用、日経サイエンス2008年1月号(SCIENTIFIC AMERICAN日本版)原題名Cell Defenses and the sunshine vitamin (SCIENTIFI AMERICAN NOVEMBER 2007 ) 80(2):68-76、2008
斉藤糧三:サーファーに花粉症はいない、株式会社小学館、東京、2012年
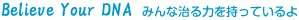

![TEL:092-554-1700 [診療時間]平日9:00~12:30・14:00~18:00/土9:00~13:00/休診日:日祝](http://fukuoka.nakamurahiroshiseikei.com/wp-content/uploads/2023/02/sp_info.png)